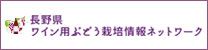研究成果『技術情報』
長野県農業関係試験場にて取り組んだ「技術情報」の研究内容とその成果をご紹介します。
|
果樹 令和2年(2020年度)果樹試験場栽培部、農業試験場企画経営部
りんご高密植栽培における着色管理回数の削減が作業時間と果実品質に及ぼす影響高密植栽培の「シナノスイート」及び「ふじ」では、慣行の2回葉摘みを1回に削減することにより、単位収量当たりの作業時間は「シナノスイート」で1~3割、「ふじ」で2~4割削減されるが、果皮色はやや劣る果実が増加する。 |
|
作物 令和2年(2020年度)農業技術課、農業試験場作物部・環境部
食味・収量情報支援コンバインと連動した乾燥システムは、タンパク質含有率に応じた仕分け乾燥調製が可能である食味・収量情報支援コンバイン、及び連動した乾燥システムを利用することで、収穫時に水分・収量・タンパク質含有率の情報を把握することができ、品質に応じて区分した乾燥調製が可能である。 |
|
作物 令和2年(2020年度)農業試験場作物部、農業技術課、松本農業農村支援センター
スマート水管理システムの水管理労働力削減効果スマート水管理システム「WATARAS」、「PaddyWatch」は水稲の水管理の省力化が可能である。いずれも水管理に出向く回数が削減されることで、「WATARAS」は80%程度、「PaddyWatch」は15%程度の省力化が見込まれる。また、慣行水管理と同等の収量を確保できる。 |
|
作物 令和2年(2020年度)農業試験場作物部・企画経営部、農業技術課
直進自動操舵、株間制御、施肥量制御機能を有する高機能田植機は、非熟練者でも精度の高い移植作業が可能である直進自動操舵、株間制御、施肥量制御機能を有する高機能田植機は、株間のばらつきが小さく、植え付け精度が高く、施肥量のばらつきが小さく、施肥精度が高く、非熟練者でも精度が高い移植作業が可能である。 |
|
作物 令和2年(2020年度)農業試験場作物部、農業技術課
自動運転トラクタを用いた効率的な2台協調作業作業者1人で、自動運転トラクタと有人トラクタを用いて行う2台協調の耕起・代かき作業は、オペレータ作業の時間短縮が図られ、効率的である。 |
|
病害虫 令和元年(2019年)野菜花き試験場佐久支場
レタス黒根病に対する感受性の品種間差レタス黒根病に対する感受性には品種間差が認められる。感受性が低い品種として、「パスポート」、「ファンファーレ」、「ルシナ8」、「バレイ」などがある。 |
|
病害虫 令和元年(2019年)野菜花き試験場環境部、佐久支場、農業技術課
「コナガコン-プラス」ロープ状製剤は設置・回収が容易な交信かく乱剤である「コナガコン-プラス」ロープ状製剤は設置・回収が容易で、ツインチューブ製剤と効果は同等だが設置時間が短く、コナガが加害するアブラナ科野菜やオオタバコガが加害するレタス等の防除上有用である。 |
|
病害虫 令和元年(2019年)野菜花き試験場環境部、農業技術課
「信州の伝統野菜」のばれいしょ「下栗芋」から検出されるウイルス種地域特産野菜の「下栗芋」からは、ジャガイモYウイルス(PVY)が広範囲に検出され、その際の病徴は「葉のえそ」及び「退緑」などである。 |
|
病害虫 令和元年(2019年)野菜花き試験場環境部、農業技術課
高温条件下でのきゅうりのモザイク病による収量低下とワクチン苗の防除効果これまで県下のきゅうりでは、キュウリモザイクウイルス(CMV)とスイカモザイクウイルス(WMV)が感染しても収量への影響が少なかったが、今後、夏季の高温化が進むと両ウイルスの重複感染で収量が低下する可能性がある。モザイク病はワクチン苗の利用により被害の軽減が期待できる。 |
|
病害虫 令和元年(2019年)南信農業試験場栽培部
カキ円星落葉病防除に有効なジマンダイセン水和剤の散布時期ジマンダイセン水和剤600倍液を6月下旬から7月上旬に1回散布すると、カキ円星落葉病を効率的に防除できる。 |
|
病害虫 令和元年(2019年)果樹試験場環境部
平地におけるブドウさび病の発生時期ブドウさび病は6月下旬から7月上旬に山林に生息する中間宿主のアワブキやミヤマハハソでさび胞子を形成し、山林から離れた平地のぶどうへの感染は7月中旬頃から始まる。10日前後の潜伏期間を経て、多発年は7月下旬頃からぶどうで夏胞子を形成し、その後収穫後まで二次感染し、発生が拡大する。 |
|
作物・病害虫 令和元年(2019年)農業試験場環境部
マメシンクイガ被害に対する大豆連作と薬剤散布時期の影響大豆連作によりマメシンクイガの発生量が増加し、子実被害が増加する。特に3年以上連作すると著しい被害が発生する場合がある。また、県内5地域における現地調査の結果から、十分な防除効果を得るには薬剤の適期散布が重要である。 |
|
作物・果樹・土壌肥料 令和元年(2019年)農業技術課、農業試験場、果樹試験場
令和元年東日本台風(台風第19号)による堆積土の土壌分析結果堆積土の土壌養分は土性によって異なり、粘質、壌質の堆積土には堆積土直下の作土に近い肥料成分が含まれ、窒素の発現も見込まれる。一方砂質の堆積土は、肥料成分が少なく窒素の発現もわずかである。 |
|
土壌肥料 令和元年(2019年)野菜花き試験場環境部
黒ボク土壌における三要素と稲わら堆肥の長期連用処理が土壌養分に及ぼす影響長期にわたる堆肥と三要素の連用試験の結果、毎年収穫物と残渣を持出した場合、稲わら堆肥を2t/10a施用しても土壌全炭素は徐々に低下し、可給態窒素は堆肥施用により増加する。 |
|
果樹・土壌肥料 令和元年(2019年)南信農業試験場栽培部
低樹高栽培のかき「市田柿」における時期別の施肥窒素吸収特性速効性の硫安を用いた11月~6月の施肥窒素は、相対的に新生器官である結果枝や果実へ多く分配され、特に6月の施肥窒素は果実への分配が多い。7月の施肥窒素は、新生器官への分配率が低下する一方、旧枝部(結果母枝~亜主枝)や主枝、主幹への分配割合が高まり、8月施肥ではその傾向がより強まる。ただし、同じ新生器官である徒長枝では、7月以降の生育後半も施肥窒素の寄与率が高く、常に施肥窒素が移行してきている。 |