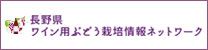研究成果『病害虫』
長野県農業関係試験場にて取り組んだ「病害虫」の研究内容とその成果をご紹介します。
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)農事試
フェロモントラップによるアカヒゲホソミドリカスミカメの発生消長の把握斑点米被害の主要加害種であるアカヒゲホソミドリカスミカメの水田内の発生消長把握にフェロモントラップ(合成性フェロモンを誘引源とする粘着トラップ)が利用可能である。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)農事試
アイガモ水稲同時作(アイガモ農法)におけるイネミズゾウムシの防除効果アイガモ水稲同時作(アイガモ農法)でアイガモは主として雑草防除対策のために導入されるが、イネミズゾウムシ防除にも効果が認められる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)南信試 下伊那普及センター
「幸水」での殺菌剤削減下における主要病害の発生「幸水」で殺菌剤の削減を行う場合、黒星病の発生に注意する必要がある。初期感染が早く多発する場合に、慣行防除と比較して被害が増加する。前年、黒星病が発生した園や常発園では殺菌剤の削減はできない。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)南信試
日本なし栽培におけるSS散布の散布時期と薬剤付着量開花期前後の葉が繁茂していない時期は、徒長枝が伸び、葉が繁茂する6月と比較すると薬剤付着量が少ない。開花前後などの初期防除ではSSの走行間隔・順路に注意するほか、授粉樹や圃場の周囲など薬剤のかかりにくい場所は手散布する必要がある。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)南信試
日本なしに発生する萎縮症状の原因と対策「幸水」に発生する萎縮症状の原因はヒポキシロン幹腐病と萎縮病が多い。いずれも木材腐朽菌による枝幹部の腐朽が原因である。治療は困難なため改植が望ましい。「南水」に発生する萎縮症状には病原菌が関与する可能性は低い。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)野菜花き試
トルコギキョウに発生する土壌伝染性ウイルス病の病原ウイルスの特定長野県と静岡県のトルコギキョウで発生している土壌伝染性ウイルス(長野株、静岡株)病害は、それぞれトンブスウイルス属の新種とトマトブッシースタントウイルス(TBSV)に起因する。さらに、静岡株はトルコギキョウえそウイルス(LNV)抗血清と極めて強い反応を示すことから LNV と TBSV は同一種である可能性が高い。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)野菜花き試
スイカ及びハクサイの生育異常症状株から分離されるウイルススイカ果面に凹凸を呈する株の黄化モザイク葉からカボチャモザイクウイルスおよびズッキーニ黄斑モザイクウイルスが、ハクサイ葉柄部外側の条状黒変部位からはカブモザイクウイルスがそれぞれ高率に検出され、これらのウイルスが生育異常に影響を及ぼしている可能性が高い。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)野菜花き試
DIBA法による植物ウイルス迅速診断体制の構築と診断症例のデータベース化長野県内の生産現場において発生するウイルス病に対して、特殊な機器を必要としない DIBA(Dot Immunobinding Assay)法を採用し、現地および研究機関が連携を図ることで、現状より迅速診断が可能となる。また、診断症例のデータベース化を図ることで、関係者各々が病徴や発病事例、発病状況などの情報を共有できる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
凍害防止によるモモ胴枯病の発病軽減モモ胴枯病は、初冬から春にかけて主幹部へのわら巻きによる凍害防止を実施することで軽減される。また、せん定を当年内に行うと胴枯病の発生が多く成るため、この時期のせん定は避ける。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
りんご品種「シナノスイート」、「シナノゴールド」、「秋映」におけるゆず果病の病徴「シナノスイート」、「秋映」でのリンゴさび果病の主な病徴は、果実の着色不良(斑入りと不均質な着色)である。「秋映」では果面にさびや凹凸が生じることがある。「シナノゴールド」では通常、無病徴である。ただし、果実が赤く着色した部位に斑入りが生じることがある。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)農事試
温湯処理前の浸水が苗立ちに及ぼす影響塩水選後温湯処理をする際は、発芽障害を回避するために、温湯処理まで極力短時間で行う。浸水が長引いた場合は、籾を乾燥させてから温湯処理を行うことにより苗立率の低下が回避できる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)農事試
県内におけるMBI-D剤耐性いもち病菌の発生実態と対策長期残効性いもち剤として県内でも広く普及されている MBI-D 剤に対する耐性菌が、平成 13 年以降西日本を中心に広く拡大している。そこで県内での MBI-D 剤耐性いもち病菌の発生実態を調査し、その対応策を示す。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)野菜花き試
タマネギ栽培跡地周辺トルコギキョウ栽培施設内外におけるネギアザミウマ誘殺消長タマネギ栽培跡地周辺のトルコギキョウ栽培施設内外では、IYSV 媒介虫であるネギアザミウマが5月中旬からに誘殺され始め、6月下旬にはタマネギ栽培跡地に面した地点で増大する。また、同時に IYSV の保毒虫率も最も高くなるが、0.6mm 目合いの寒冷紗で被覆した施設内においてはその程度は低く推移する。 |
|
普及技術 平成17年(2005年)水産試
新しい農薬の魚類に対する急性毒性ニジマス、コイに対して、オンリーワンフロアブルは毒性が低い |
|
普及技術 平成17年(2005年)野菜花き試
トルコギキョウにえそ症状を引き起こす新規トンブスウイルスとその血清学的診断法県内のトルコギキョウ栽培施設においてえそ症状を呈する株から外被タンパクが39~40Kdaの分子量を持つ球状ウイルスが分離され,諸性質を調べ特定を行ったところ,新規のトンブスウイルスであることが判明した。また,本ウイルスに対する抗血清を作製し,血清学的診断法を確立した。 |