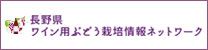研究成果『果樹』
長野県農業関係試験場にて取り組んだ「果樹」の研究内容とその成果をご紹介します。
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)南信試 下伊那普及センター
「幸水」での殺菌剤削減下における主要病害の発生「幸水」で殺菌剤の削減を行う場合、黒星病の発生に注意する必要がある。初期感染が早く多発する場合に、慣行防除と比較して被害が増加する。前年、黒星病が発生した園や常発園では殺菌剤の削減はできない。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)南信試
日本なし栽培におけるSS散布の散布時期と薬剤付着量開花期前後の葉が繁茂していない時期は、徒長枝が伸び、葉が繁茂する6月と比較すると薬剤付着量が少ない。開花前後などの初期防除ではSSの走行間隔・順路に注意するほか、授粉樹や圃場の周囲など薬剤のかかりにくい場所は手散布する必要がある。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)南信試
日本なしに発生する萎縮症状の原因と対策「幸水」に発生する萎縮症状の原因はヒポキシロン幹腐病と萎縮病が多い。いずれも木材腐朽菌による枝幹部の腐朽が原因である。治療は困難なため改植が望ましい。「南水」に発生する萎縮症状には病原菌が関与する可能性は低い。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
凍害防止によるモモ胴枯病の発病軽減モモ胴枯病は、初冬から春にかけて主幹部へのわら巻きによる凍害防止を実施することで軽減される。また、せん定を当年内に行うと胴枯病の発生が多く成るため、この時期のせん定は避ける。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
りんご品種「シナノスイート」、「シナノゴールド」、「秋映」におけるゆず果病の病徴「シナノスイート」、「秋映」でのリンゴさび果病の主な病徴は、果実の着色不良(斑入りと不均質な着色)である。「秋映」では果面にさびや凹凸が生じることがある。「シナノゴールド」では通常、無病徴である。ただし、果実が赤く着色した部位に斑入りが生じることがある。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)農総試
ブームスプレーヤ用ドリフト軽減ノズル「エコシャワー」はドリフトが少なく、慣行ノズルの補完として利用できるドリフト低減ノズル「エコシャワー」は、ドリフトが少ないブームスプレーヤ用ノズルとして有用である。防除効果は慣行ノズルと同等またはやや劣る場合があるので、慣行ノズルの補完としてドリフトを避けたい場合に利用できる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)南信試
干し柿「市田柿」の加工は適熟果を利用する未熟な原料果実から加工した干し柿「市田柿」は、貯蔵中に粉の戻りが発生しやすく、商品価値が低下するので、干し柿「市田柿」の加工には適熟果を使用する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
日本すもも「貴陽」の受粉樹の選定と受粉時期の把握日本すもも「貴陽」の受粉樹として、「ハリウッド」、「エレファントハート」が適している。受粉時期は、開花が5分咲きの頃から落花が始まる頃までの期間であり、人工受粉を必ず実施する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
もも晩生種「モモ長果8」の育成9月上中旬に成熟し、果実の大きさが400g前後の大玉で、着色が良く、外観が優れる「モモ長果8」を育成した。本品種はもも品種の中ではかなり遅い時期に収穫できる品種に位置づけられ、全国的に見ても遅く出荷できる品種にあたるため、晩生種として期待できる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
もも品種・台木の組み合わせと凍害発生もも品種「川中島白鳳」は「川中島白桃」に比べ、また、もも台木「おはつもも」は「筑波4号」に比べ凍害発生が多く、特に、「川中島白鳳」と「おはつもも」の組み合わせで発生が増加する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
ぶどう「ナガノパープル」の果皮色による収穫適期の把握法ぶどう「ナガノパープル」は、満開後85日以降、果てい部まで赤紫色に着色した果房を収穫することで、18%以上の糖度が得られる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
りんご「メイポール」の省力的な花芽確保法りんご「メイポ-ル」は、落花後に1年枝を基部3芽程度残して切除するだけで、摘果作業を行わなくても翌年の花芽が確保できる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
りんごわい性台木苗木の新梢先端部へのビーエー液剤の繰り返し散布は、フェザー発生促進効果が高いりんごのわい性台木を用いたフェザー付きの 2 年生苗木育成において、苗木育成 2 年目に、伸長中の苗木新梢の先端部へビーエー液剤を繰り返し(5 回以内)散布する。散布回数が多いほど、新梢上に多数のフェザーが発生する。 |
|
普及技術 平成17年(2005年)南信試
整枝せん定法.施肥法.土壌改良法の改善技術の組み合わせによる「幸水」の樹勢回復と増収効果「幸水」の低位生産園では、側枝密度、長果枝側枝比率を改善した整枝せん定法、窒素肥料を年4回に分肥する施肥法、部分深耕と堆肥局所施肥による土壌改良法の組み合わせにより、樹勢回復と増収効果が得られる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成17年(2005年)果樹試
りんご「JM7」台木樹の接ぎ木部のコブ発生(227KB)りんご「JM7」台木樹で、樹齢の経過とともに接ぎ木部に粗皮状のコブが発生して、特に「ふじ」との組み合わせで樹勢衰弱がみられることがある。 |