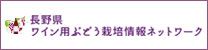クロバネキノコバエ科(きのこ/ブナシメジ)

病徴と診断
菌床栽培で発生するクロバネキノコバエには、ツクリタケクロバネキノコバエ(写真4)、チビ(チバ)クロバネキノコバエなどが報告されている。 チバクロバネとチビクロバネは別種として扱われていたが、近年の研究では同種と扱われることが多くなった。日本産のクロバネキノコバエ科は21属113種の記録があるが、実際はこの10~20倍の種がいると推測されており、分類は非常に難しい。また、未成熟期(幼虫)の形態については研究が非常に少なく、幼虫による同定は不可能とされている。
成虫の体長が2~5mmの小さなハエで、全体が黒っぽい色をしており、2枚の羽は透明~暗色透明で、頭部には糸状の長い触角を持つ。この仲間の1種の飼育例では、1世代が18日前後(20~30℃)である。卵は楕円形で淡い色をしており、菌床に産みつけられる。幼虫は体長3~8mm、体色が透明~黄色で、菌床に穴を掘って菌糸を食する。キチン質の頑丈な口吻を持ち、きのこ組織を食い破り、穿孔することもある。10日程度で簡単な繭を作り蛹になる。繭を作る場所は外界に近い菌床内や種菌上である。蛹は数日で成虫になる。
発病条件
深刻な被害は培養ビン内への侵入と害菌汚染の拡大である。培養期間が長いブナシメジでは培養ビン内で羽化した成虫が他の培養ビンへと移動して、害菌汚染を広げ、培養室内で繁殖を繰り返すことで、害菌被害が拡大しやすい。侵入される培養ビンの多くは割れているか(特に底面)、破損キャップやキャップフィルターが古くなり収縮した不良ビンがほとんどである。培養日数の短いエノキタケやヒラタケの場合、菌かき時に外したキャップや菌床面に幼虫や蛹を発見することで、その侵入に気づくことが多い。
菌かきの前に抜き取った汚染ビンを、菌かき機や生育室周辺に放置すると成虫が出てきて、生育室内の菌かき後ビンの菌床面や生育の遅いビンに産卵する。また、ブナシメジ生育室棚のコケ(ヤノウエノアカゴケ等)や汚れた壁や床などでも繁殖が確認されているので、生育室の定期的な洗浄は必須である。
防除方法
・培養室の吸排気口への侵入防止ネットの設置、隙間を埋める
・培養室入り口にエアー(ビニール)カーテンを設置し、成虫の侵入を防ぐ
・割れビン・破損キャップの処分、キャップのウレタンフィルターの交換
・害菌汚染ビンの抜き取り徹底
・培養室に捕虫機の設置
・種菌量の確認(特にブナシメジ)※菌床面とキャップ間に隙間があると産卵されやすい
・汚染ビンを生育室や菌かき機周辺に放置しない
・施設周辺に廃菌床、割れビン等を放置しない
・生息場所となる、施設周辺の雑草は定期的に草刈りする等を定期的に実施する。