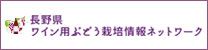わたかび病(きのこ/エノキタケ)

病徴と診断
エノキタケ生育中に子実体の株元から白い菌糸が厚く覆い、子実体を溶かし、やがて萎れて最後は枯死する。接種から生育前期までに感染すると、子実体への被害が大きい。菌糸、胞子ともに白いため、エノキタケでは特に発見が遅れがちとなり、注意が必要である。本病菌の分離には、わたかび病菌選択培地RM3培地を用いる(https://www.agries-nagano.jp/research/genre03)。被害ビンから釣菌するか、栽培施設において落下菌や付着菌を採取し、20℃で培養し、培養後コロニーを観察し診断する。
発病条件
本病は、糸状菌のクラドボトリウム・バリウムが原因菌である。低温性の糸状菌であり、エノキタケ生育室でも繁殖し、胞子が飛散する。そのため、冬~初春にかけての寒い季節の被害が多い。子実体にわた状の菌糸が発生するころには胞子が多量に飛散し、それらが施設全体を汚染して被害が拡大する。接種室等での空気感染、菌かき機や巻紙からの接触による感染、収穫時等の被害株への接触で胞子が飛散し、被害を拡大させる。
防除方法
1.被害ビン・株の抜き取り直ちに殺菌処分
2.菌かき機刃の除菌、巻紙の洗浄等
3.被害株への接触による胞子飛散対策(作業者の専任等)
4.詰め場等での粉塵飛散防止対策
5.施設内の清掃および除菌