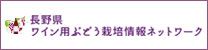黒腐細菌病(きのこ/エノキタケ)

病徴と診断
主にエノキタケの子実体を侵す。芽出し以降に黒いアメ状の液体が菌床に発生して株元等を黒く腐らせる。菌床での被害は少ないが、病原細菌はエノキタケ菌糸と共存し、エノキタケの子実体が芽を出すと子実体を腐敗させる。本病菌の分離には、黒腐細菌病菌選択培地TSM-10培地を用いる(https://www.agries-nagano.jp/research/genre03)。被害株から組織分離するか、栽培施設において付着菌や汚染水を採取し、TSM-10培地で培養後、特徴的なコロニーを観察する。選択培地による診断が難しい場合は、培地に生じたコロニーをエノキタケに接種する「簡易病原性検定法」により病原性の有無を確認できる。
発病条件
本病は、細菌のシュードモナス・トラシーが原因菌である。低温でも生育できる細菌であるため、エノキタケ栽培施設の環境に適応性が高い。きのこ施設では一般的な細菌であり、栽培施設の床にある、きのこ培地の残渣、溜水等で生存している。加湿器の霧や結露水等の水由来で感染する場合が多い。また、菌かき機による伝染・拡大事例も多く、汚染した菌かき水も発生を助長させる。
防除方法
1.冷却器、加湿器等の定期的な点検、清掃
2.菌かき機刃の除菌
3.被害ビン・株の抜き取り直ちに殺菌処分
4.施設内の清掃および除菌