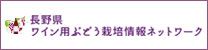桃色かび立枯病(きのこ/エノキタケ)

病徴と診断
エノキタケ子実体の芽出し前後に、菌床面に淡い桃色の胞子を多数生産し、芽出し不良を起こす。接種から生育前期までに感染すると、罹病株として被害が確認される。接種時など、早い時期に感染するほど被害は大きい。本病はエノキタケ黒腐細菌病との併発が多くみられる。本病菌の分離には、RBC培地またはRM3培地を用いる(https://www.agries-nagano.jp/research/genre03)。被害ビンから釣菌したり、栽培施設において落下菌や付着菌を採取し、培養後にコロニーを観察して診断する。
発病条件
本病は、糸状菌のスピセルム・ロゼウムが原因菌である。春~初夏にかけての比較的温かい季節に被害が多いが、栽培施設内では通年で生存すると考えられる。胞子が飛散しやすいため、接種室等での空気感染、菌かき機・巻紙からの接触による感染で被害が拡大し、施設全体が汚染されると考えられる。
防除方法
1.詰め場等での粉塵飛散防止対策
2.菌かき機刃の除菌、巻紙の洗浄等
3.被害ビン・株の抜き取り直ちに殺菌処分
4.施設内の清掃および除菌